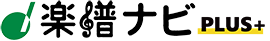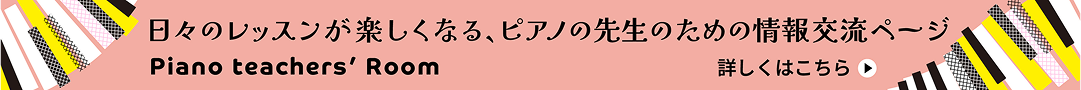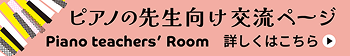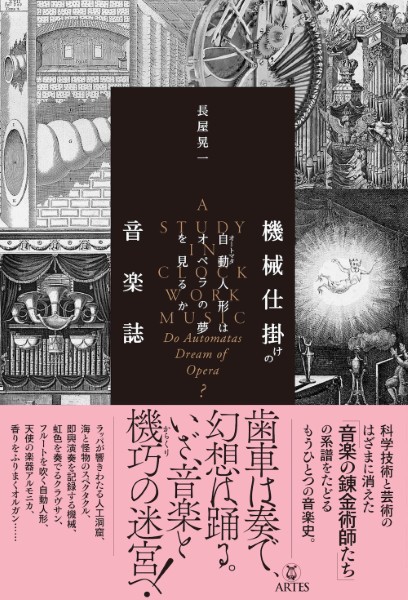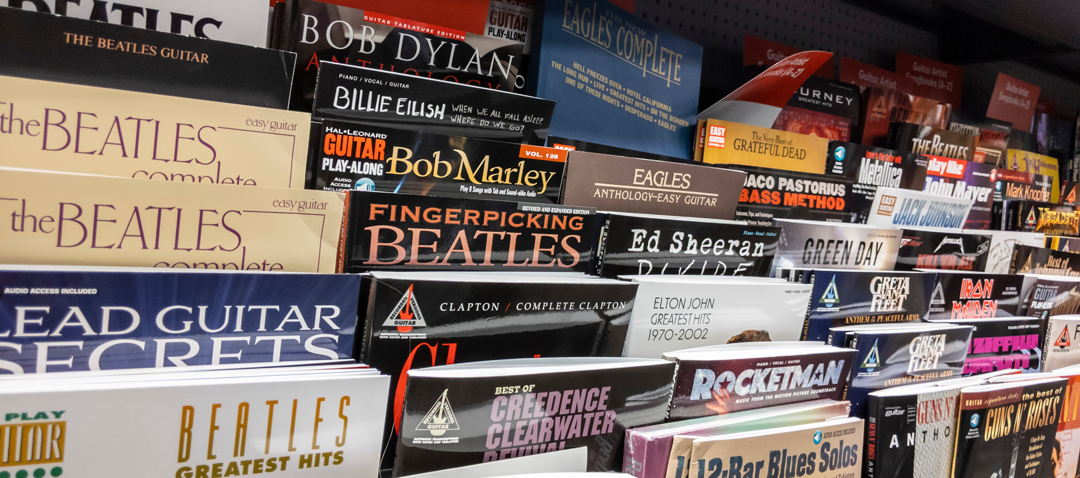歌え、人造のミューズよ。
科学技術と芸術のはざまに消えた
「音楽の錬金術師たち」の系譜をたどる
もうひとつの音楽史。
歯車は奏で、幻想は踊る。
いざ、音楽と機巧(からくり)の迷宮へ!
ラッパが響きわたる人工洞窟、
海と怪物のスペクタクル、
即興演奏を記録する機械、
虹色を奏でるクラヴサン、
フルートを吹く自動人形、
天使の楽器アルモニカ、
香りをふりまくオルガン・・・・・・
命なき楽士たちがつづる500年の音楽史。
音楽は人の手が楽器を鳴らして演奏するもの、人が声を発して歌うものだ。そういう常識の片隅でわたしたちは、機械じたいが鳴らす音楽に心惹かれずにはいられない。
──「前口上 機械が歌をうたうとき」より
人を驚かせたいという願望が自動人形や自動演奏機械、早変わりする舞台装置を生み出した。アルモニカの音色、ファンタスマゴリーの誘惑、色と音と香りの共鳴、そこには人間の認識にたいする科学の夢がある。あるいは、消えてしまう即興演奏を書きとめようとする試み、これはレコーディング、そして現代の打ち込み式の楽譜入力で可能になった。しかし、その思想・願望は18世紀には生まれ、それほど現代とは異ならないかたちで提案されていた。ただその当時の技術が追いついていなかっただけである。
──「あとがき」より
『月刊アルテス』好評連載、待望の書籍化!
◎著者プロフィール
長屋晃一(ながや・こういち)
1983年生まれ。愛知県出身。國學院大學文学部卒(考古学)。慶應義塾大学大学院文学研究科にて音楽学を学ぶ・博士課程単位取得退学。修士(芸術学)。現在、立教大学、慶應義塾大学ほか非常勤講師。19世紀のイタリア・オペラにおける音楽と演出の関係、オペラ・音楽劇のドラマトゥルギーについて研究をおこなう。
著書に『ミュージカルの解剖学』(春秋社、2024)、論文に「ヴェルディにおける音楽の「色合い」:《ドミノの復讐》の検閲をめぐる資料から」(『國學院雑誌』、2023)、「音楽化される川端康成:歌謡曲からオペラまで」(共著『〈転生〉する川端康成 I──引用・オマージュの諸相』、文学通信、2024)などがある。
研究に加えて、舞台やオペラの脚本も手がける。オペラ《ハーメルンの笛吹き男》(一柳慧作曲、田尾下哲との共同脚本、2013)、音楽狂言『寿来爺(SUKURUJI)』(ヴァルター・ギーガー作曲、2015)ほか。
◎目次
前口上|機械が歌をうたうとき
1|プラトリーノの秘密の洞窟
2|天界から地獄まで
3|アルチンボルドのひそかな企み
4|波間の怪物
5|エステ荘の水の戯れ
6|キルヒャー師を訪ねて
7|太鼓よとどろけ!
8|失われた音をもとめて
9|虹色クラヴサン
10|鼓笛童子春壽(こてきどうじはるのことほぎ)
11|レントゲン式収納術
12|王妃に捧げるオートマタ
13|?人形師の自動オルガン
14|天使の音色──グラス・ハーモニカ興亡史(1)
15|デイヴィス姉妹──グラス・ハーモニカ興亡史(2)
16|天使のごときマリアンネ──グラス・ハーモニカ興亡史(3)
17|メトロノームとパンハルモニコン
18|狼谷は危険な香り
19|幽霊たちが歩きだす
20|バレリーナ幻想
21|香りの音階
22|純粋な響きをもとめて──ブルックナーと田中正平
23|自動ピアノのための練習曲
24|音楽の小箱
あとがき

近隣店舗の在庫状況
※お近くの店舗から順に表示しています。
※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。