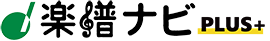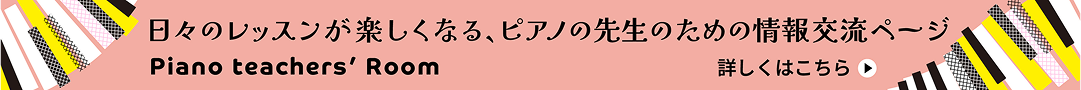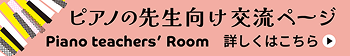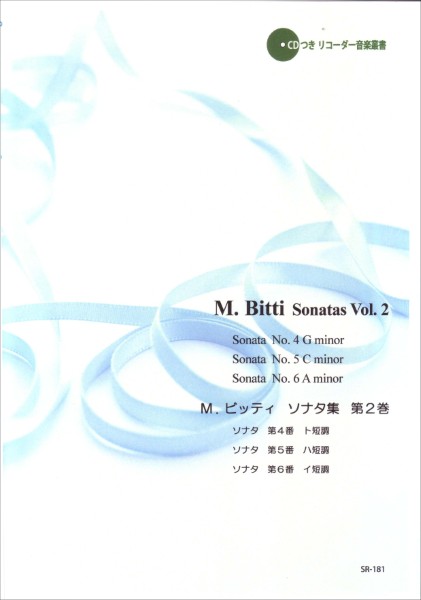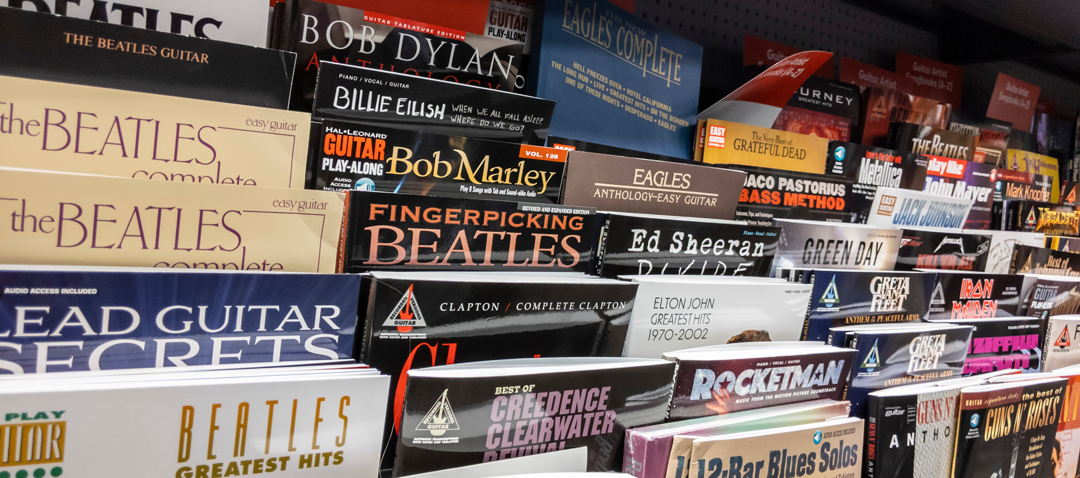ソナタ 第4番 ト短調
★解題★
M.ビッティの「チェンバロまたはバス・ヴァイオリンの通奏低音を伴うアルトリコーダー独奏曲集(Solos for a flute, with a th[o]rough bass for the harpsicord or bass violin)」と題された、8曲から成るアルトリコーダーのためのソナタ集は、ロンドンのWalshから1711年に出版されました。(タイトルに誤りがあったため翌年に再版されました。上記のタイトルは訂正後のものです。)
★解説★
4楽章から成り、ゆったりとしたプレリュードに続いて3つの舞曲が並べられた「室内ソナタ」型のソナタです。どの楽章も音楽的密度が高く、ひきしまった名品です。
第1楽章は2分の3拍子で、ラルゴ(広々と)と指定されたプレリュードです。わかりやすく話の進む内容ですので、気持ちを乗せていきやすいでしょう。かなり多くの音符にまたがるスラーが多用されており、いくらか「ヴァイオリン寄り」の書法を感じさせますが、リコーダーでもなかなか面白い効果が上がります。
第2楽章は4分の4拍子のアルマンドで、ヴィヴァーチェ(生き生きと)指定されています。リコーダーがキビキビとしたテーマで先導し、低音が模倣して始まります。シンコペーションのモチーフが随所で用いられているのが耳に残ります。
第3楽章はアレグロ(快活に)と指定された4分の3拍子のコレンテです。第1楽章と同様、いくらか長めの(多数の音にまたがる)スラーがよく用いられており、面白い効果を上げますが、きれいに演奏するのがなかなか難しくなる原因にもなっています。
第4楽章は2分の2拍子のガボットで、プレスト(速く)と指定されてます。すばしこい感じのテーマで始まり、短いながらも多彩な表情をみせながら駆け抜けていきます。
※演奏例がお聴きいただけます
■リコーダーによる演奏
第1楽章(B2)
第2楽章(C1)
第3楽章(B3)
第4楽章(B3)
※カッコ内は指回り難度です。
※リコーダー演奏:石田誠司 (全音 G-1A 使用)
チェンバロ演奏: 石田誠司 (使用楽器はRJP所有のデジタルサンプリング音源)
★解題★
M.ビッティの「チェンバロまたはバス・ヴァイオリンの通奏低音を伴うアルトリコーダー独奏曲集(Solos for a flute, with a th[o]rough bass for the harpsicord or bass violin)」と題された、8曲から成るアルトリコーダーのためのソナタ集は、ロンドンのWalshから1711年に出版されました。(タイトルに誤りがあったため翌年に再版されました。上記のタイトルは訂正後のものです。)
★解説★
4楽章から成り、プレリュードに3つの舞曲が続くという形をとっています。しかし、第2楽章・第3楽章は舞曲のタイトルを持ちながらも対位法的な味わいが濃厚な名品で、異色の傑作だと言えるでしょう。
第1楽章はアンダンテ(歩くように)と指定されたプレリュードで、4分の4拍子です。前半・後半それぞれを繰り返す二部形式で、おもに16分音符で旋律を描く部分と三連符の動きになる部分が組み合わされて、美しく歌われます。終わり近くに、三連符の連続で、転がり落ちていくような加速感のあるフレーズが印象的です。
第2楽章は8分の12拍子のジーグで、アレグロ(快活に)と指定されています。リコーダーが先行し、低音がそれを模倣して始まり、以下、互いを模倣するようなやりとりの多い音楽になっています。後半に出てくる、「係留音」を利かせて美しく下降するゼクエンツが絶品で、「こんなジーグは他にないな」と感じさせてくれます。最後は高揚感とスピード感のある収束の音楽が待っています。
第3楽章は4分の3拍子で、ヴィヴァーチェ(生き生きと)と指定されたコレンテです。これもジーグと同様にリコーダーが先行して低音がそれを模倣して始まり、やはり全編にわたって互いを模倣する対話的な進行が多く、まるでフーガのような雰囲気の音楽になっています。
第4楽章はプレスト(速く)、2分の2拍子のガボットです。キビキビと進む快適な音楽をくりひろげた上で、最後は「ナポリ6」の和音を効果的に用いてひっそりと全曲をしめくくります。
※演奏例がお聴きいただけます
■リコーダーによる演奏
第1楽章(B3)
第2楽章(C1)
第3楽章(B3)
第4楽章(C1)
※カッコ内は指回り難度です。
※リコーダー演奏:石田誠司 (全音 G-1A 使用)
チェンバロ演奏: 石田誠司 (使用楽器はRJP所有のデジタルサンプリング音源)
ソナタ 第5番 ハ短調
★解題★
M.ビッティの「チェンバロまたはバス・ヴァイオリンの通奏低音を伴うアルトリコーダー独奏曲集(Solos for a flute, with a th[o]rough bass for the harpsicord or bass violin)」と題された、8曲から成るアルトリコーダーのためのソナタ集は、ロンドンのWalshから1711年に出版されました。(タイトルに誤りがあったため翌年に再版されました。上記のタイトルは訂正後のものです。)
★解説★
4楽章から成っています。斬新な第1楽章から始まり、全編にわたり創意に富んだ傑作です。「ナポリ6和音」をよく効果的に用いているのも印象的。
第1楽章はラルゴ(広々と)と指定されたプレリュードで、4分の4拍子です。まず通奏低音だけによる前奏があって、まるでタンゴのようなリズムの低音が奏されます。これを何度も繰り返す上で旋律楽器が歌うという、「グラウンド」の手法を取り入れた楽章で、途中で転調もまじえる工夫も心憎いばかりの効果を上げています。
第2楽章は4分の4拍子のアルマンドで、アレグロ(快活に)と指定されています。「フラット2つ」の調の速いテンポの楽曲としては指運びの困難が比較的少なくて快調に演奏できますが、後半、32分音符が何度も出てくるので、そう無茶な速いテンポにするわけにもいかないでしょう。
第3楽章はラルゴ(広々と)と指定されたサラバンドで、2分の3拍子、まさに広々とした感じの雄大な音楽です。開始のところが(マイナスワンに合うように演奏するのは)少し難しいのですが、低音奏者との生セッションなら相手が合わせてくれるでしょう。
第4楽章は、アレグロ、8分の12拍子のジーグです。イタリアのジーグですから、かなり速いテンポが本来かも知れませんが、和声もリズムも実に面白いので、演奏例のように少し遅めのテンポでじっくりと味わってみるのも悪くないと思います。魅惑的で力強い、絶品の終曲です。
※演奏例がお聴きいただけます
■リコーダーによる演奏
第1楽章(B2)
第2楽章(C1)
第3楽章(C1)
第4楽章(C1)
※カッコ内は指回り難度です。
※リコーダー演奏:石田誠司 (全音 G-1A 使用)
チェンバロ演奏: 石田誠司 (使用楽器はRJP所有のデジタルサンプリング音源)
ソナタ 第6番 イ短調

近隣店舗の在庫状況
※お近くの店舗から順に表示しています。
※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。