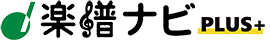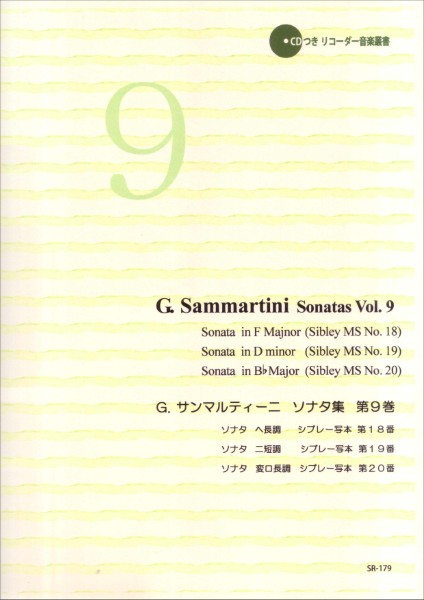ウクレレ/カリンバ その他楽器
- HOME
- SR-179 サンマルティーニ ソナタ集 第9巻
G.サンマルティーニ ソナタ ヘ長調 シブレー写本第18番
★解題★
サンマルティーニの通奏低音つきソロソナタばかり27曲を集めた、「シブレー写本(Sibley Manuscript)」と呼ばれる筆写譜があります(ロチェスター大学所蔵)。このうち16曲がリコーダー用のソナタで、最大の数を占めています。(ほかはオーボエ用、ヴァイオリン用、横吹きフルート用など。)
サンマルティーニのリコーダー用ソナタの出版作品はあまりたくさん残っていませんので、これが貴重なソースになっています。
★解説★
3楽章から成り、気宇の壮大な、すばらしい傑作です。
第1楽章はアレグロ(快活に)、4分の2拍子です。かろやかな第1主題で始まり、一度アダージョに落としてしなかやに半終始。続いてテーマを確保した後、天から舞い降りるような16分音符の経過句を挟んで、シンコペーションのリズムに続いて分散和音をはなやかにくりひろげる第2テーマ(ハ長調)を示し、前半をしめくくります。後半は再び主調で主題を奏することで始まり、前半で提示した素材を用いながら自由な展開が行われ、第1主題の再現は省いて、第2主題のはなやかな分散和音の音型で収束に向かいます。
第2楽章はアンダンテ(歩くように)、ニ短調・4分の4拍子です。付点の跳ねるリズムを土台に、32分音符まで用いる細かに刺繍された主題を扱い、次々に調を移りながらしだいに競り上がるように緊張を高めていきます。ようやくイ短調に一度終止すると、以後は全体として下降し沈静化する傾向の音楽になり、ここで初めて三連符も登場して効果を上げます。やがて最後は「ナポリ」の和音を効果的にしばらく響かせて、しめやかに終わる‥‥のかと思いきや、突如、激しく半音階的に競りあがっていく劇的な終結部が強い印象を残して終わります。
第3楽章は再びアレグロで、4分の3拍子の堂々たる終曲です。気品のあるかろやかな主題で始まり、八分音符で「ひとり2声」の部分を含む音型、三連符を用いて競りあがっていく音型などの素材を示しながら語り進め、ハ長調で前半をしめくくります。後半は、前半に示した素材を用いて、変化に富み緊張感あふれる展開が行われ、圧巻の壮大なクライマックスを築きます。その後はいくらか回想もまじえながら収束へ進み、最後は主和音の分散和音を念入りに重ねてまとめています。
第1楽章(C-2)
第2楽章(C-1)
第3楽章(C-2)
※カッコ内は指回り難度です。
G.サンマルティーニ ソナタ ニ短調 シブレー写本第19番
★解題★
サンマルティーニの通奏低音つきソロソナタばかり27曲を集めた、「シブレー写本(Sibley Manuscript)」と呼ばれる筆写譜があります(ロチェスター大学所蔵)。このうち16曲がリコーダー用のソナタで、最大の数を占めています。(ほかはオーボエ用、ヴァイオリン用、横吹きフルート用など。)
サンマルティーニのリコーダー用ソナタの出版作品はあまりたくさん残っていませんので、これが貴重なソースになっています。
★解説★
3つの楽章から成り、力強く輝かしい傑作です。
第1楽章はアレグロ・ノン・タント(やや快活[快速]に)、4分の3拍子です。力強いテーマで始まる第1主題部は緊迫感に満ちています。決然とした3小節のモチーフに続き、「頭欠け下降音階」が歌われ、これが楽章全体を通じてさまざまな表情をみせながら重要な役割を担います。平行長調(ヘ長調)に転じて第2主題部は対照的に伸びやかな魅惑に満ちていますが、ここでも「頭欠け下降音階」がきかれます。繰り返しのあと後半は、新しいリズム型も取り入れながら圧倒的な高揚をみせます。後年の「ソナタ形式」なら「再現部」に進むところですが、ここではこの後も主題がはっきりと再現されることなく進み、やがて収束に入ると、フェルマータにより一呼吸を置いて気息を整えて(あるいは華やかなアドリブをあしらって)からしめくくります。
第2楽章はアンダンテ(歩くように[ゆっくりと])、変ロ長調で、4分の4拍子です。付点リズムと三連リズムをまじえながら下降音型を中心に形成されたやすらかな感じの主題で始まります。実はこの主題には第1楽章の主題と共通する音程関係が含まれており、全曲の統一性を強める工夫が隠されています。細かな音符まで駆使してきめ細かく歌っていき、前半にもかなり力強いクライマックスがあります。後半に入ると間もなく前打音的な三連符に続いていきなり「減七の和音」を叩きつけ、ニ短調からイ短調・ト短調へとめまぐるしく移りながら激しい感情をほとばしらせますが、やがて明るんで静まった部分の夢見るような美しさも絶品です。最後は前半の収束部分を再現しながらしめくくります。
第3楽章はアレグロ(快活[快速]に)、4分の2拍子です。第1楽章の主題から抽出された、決然とした主題で始まります。スピード感あふれる推移部では、さまざまなリズム型や音型を次々に導入していきます。やがてヘ長調の第2主題部に入ると、ここではもっぱら三連リズムで音楽を繰り広げます。後半に入ると、前半部で示した素材を縦横に駆使しながら密度高く展開を行います。そして第1楽章と同様に主題の再現は行われないまま、やがて三連リズムの音楽になると、それが合図であったかのように収束に入っていきます。
第1楽章(C-2)
第2楽章(C-1)
第3楽章(C-2)
※カッコ内は指回り難度です。
G.サンマルティーニ ソナタ 変ロ長調 シブレー写本第20番
★解題★
サンマルティーニの通奏低音つきソロソナタばかり27曲を集めた、「シブレー写本(Sibley Manuscript)」と呼ばれる筆写譜があります(ロチェスター大学所蔵)。このうち16曲がリコーダー用のソナタで、最大の数を占めています。(ほかはオーボエ用、ヴァイオリン用、横吹きフルート用など。)
サンマルティーニのリコーダー用ソナタの出版作品はあまりたくさん残っていませんので、これが貴重なソースになっています。
★解説★
3つの楽章から成っています。どの楽章もすばらしく充実した名品です。
第1楽章はアレグロ(快活に)、4分の4拍子です。上行分散和音音型で始まる力強い主題で始まりますが、突如、短調の早口なパッセージが雰囲気を変え、シンコペーションのリズムを含むひろびろとした感じの第二主題を導きます。前半部の収束は、「リコーダーが高音保続音(高いドの連打)を含む分散和音、低音はシンコペーションのリズムで係留音をともないつつ音階的に下降」という独創的な音楽。後半は第1主題をヘ長調で示して始まって、変化に富む音楽をくりひろげますが、第2主題のモチーフが重要な役割を果たします。
第2楽章はアンダンテ(歩くように)、4分の4拍子で、主調・変ロ長調の平行短調であるト短調の楽章です。1小節の1拍目に3音の重音が書かれているのは、ヴァイオリンで演奏する場合のための音でしょう。リコーダーでは一番上の「ソ」を吹いておけばいいと思います。付点リズム、三連リズム、そして32分音符によるモチーフなど多彩なリズムを駆使して、大きな感情の起伏を描いていきます。
第3楽章は再びアレグロで、4分の2拍子、スピード感あふれる颯爽とした終曲で、下降音階を含むくっきりとした輪郭のテーマで始まります。この「音階的下降」は、楽章を通じて大きな役割を果たします。ヘ長調の第二テーマは経過句のような軽い印象のもので、やがて16分音符による華やかなパッセージを導きます。後半は主題の材料を用いながら語り進めますが、前半には現れなかった三連リズムを導入して、かなり活躍させています。
第1楽章(C-2)
第2楽章(C-1)
第3楽章(C-2)
※カッコ内は指回り難度です。
NULL

近隣店舗の在庫状況
※お近くの店舗から順に表示しています。
※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。